今回は、FP2級でも頻出テーマである「社会保険」の基礎についてまとめます。また健康保険についての概要を解説します。特に医療保険制度に関する出題は多いため、仕組みや違いを押さえておきましょう。
社会保険とは?
- 社会保険は、国が運営する保険制度です。
- 加入が法律で義務づけられており、該当するすべての人が加入します。
- 社会保険は、狭義では医療保険、介護保険、年金保険を指します。労災保険や雇用保険などの労働に関する保険を含めて、社会保険とする場合もあります。
社会保険の分類
| 種類 | 対象となるリスク | 主な加入対象 |
|---|---|---|
| 医療保険 | 病気・けが | 全国民(職業により異なる) |
| 介護保険 | 要介護状態 | 40歳以上 |
| 年金保険 | 老後・障害・死亡 | 全国民 |
公的医療保険制度の全体像
日本では「国民皆保険制度」が採用されており、全員が何らかの公的医療保険に加入します。
| 制度名 | 対象者 |
|---|---|
| 健康保険(健保) | 会社員等とその被扶養者 |
| 共済組合 | 公務員等とその被扶養者 |
| 国民健康保険(国保) | 自営業・フリーランス等 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の高齢者 |
※ FP試験では、健康保険(健保)が最重要。まずはここを中心に覚えましょう。
健康保険の仕組み
- 保険者:保険を運営する側(例:全国健康保険協会、健康保険組合)
- 被保険者:保険の対象となる私たち(加入者)
- 保険料は、会社が給与から天引きして支払います。
- 病院では、原則3割を自己負担、残り7割は保険者が支払います。
健康保険の2つの種類
| 名称 | 運営主体 | 対象企業 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会 | 主に中小企業の従業員 |
| 組合健保 | 健康保険組合 | 大企業(一定以上の従業員数) |
- 組合健保を設立するには、一定以上の規模(従業員数など)が必要。
- 中小企業では単独で組合を作れないため、協会けんぽに加入します。
健康保険の被保険者
健康保険の適用事業所で働く人は、原則として、健康保険の被保険者となります。パートタイマー・アルバイト等は、次の場合に原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同一事業所に使用される通常の労働者の4分3以上である場合
- 下記のすべてを満たしている場合
①所定労働時間が週20時間以上である場合
②月額賃金が8.8万円以上
③2ヶ月を超える雇用見込みがある
④学生ではない
⑤従業員数51人以上の企業等に勤務していること
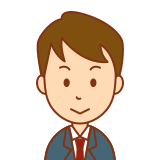
月額8.8万円×12ヶ月=約106万円。いわゆる社会保険の106万円の壁といわれるものとなります。
⑤の従業員要件はどんどん少なくなっているので、壁が強固になってきています。
健康保険の被扶養者
被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚関係含む)、子、孫など3親等以内の親族で、主として被保険者の収入により生計を維持され、日本国内に住所を有する者は、健康保険の「被扶養者」となることができます。
必要なる年収条件
- 年収130万円未満(60歳以上または一定の障害者である場合は年収180万円未満
- 被保険者と同一世帯に属している場合、被保険者の年収の2分の1未満
- 被保険者の同一世帯に属していない場合(別居の場合)、被保険者の援助による収入より少ないこと
被扶養者は、被保険者と同様に、病気やケガをしたときなどに、健康保険からの保険給付を受けることができます。
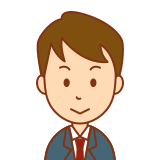
国民健康保険には、被扶養者という概念はありません。ここでは健康保険についての話となります
健康保険の保険料
健康保険の保険料は、報酬と賞与を元に計算し、徴収されます。毎月の保険料は「標準報酬月額」を基礎として計算されます。保険料の支払いは、原則、会社と被保険者が半分ずつ労使折半となります。
標準報酬月額とは、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を計算するために、被保険者(従業員)が得た給与などのひと月分の報酬を一定の範囲ごとに区分したものです。この区分は「等級」と呼ばれ、健康保険では50等級、厚生年金保険では32等級に分けられています
※給与なので、通勤手当を含む各種手当てや残業代なども含みます。
協会けんぽではの保険料率は、都道府県ごとに異なります。ただし介護保険料率は、全国一律となっています。
なお、産前産後休業、育児休業の期間は、事業主が申出をすることで被保険者負担分および、事業主負担分の健康保険料(厚生年金保険料も)が免除となります。
健康保険の給付
健康保険の給付には、主に次のものがあります。
病気やケガ
健康保険証(被保険者証)での受診
- 療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)
- 入院時食事療養費(被扶養者の場合は家族療養費)
- 入院時生活療養費(被扶養者の場合は家族療養費)
- 保険外併用療養費(被扶養者の場合は家族療養費)
- 訪問看護療養費(被扶養者の場合は家族訪問看護療養費)
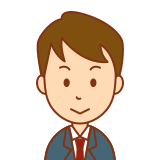
一番多いであろう、普段病院を利用する際は「療養の給付」が適用されています
診療代の立替払い
- 療養費(被扶養者の場合は家族療養費)
- 高額療養費
- 移送費(被扶養者の場合は家族移送費)
療養のための欠勤
- 傷病手当金
被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して3日休んだ後、休業4日目以降の労務ができず、報酬が得られない場合に支給されます。
標準報酬日額の3分の2の金額が通算で1年6ヶ月間を限度に支給されます。
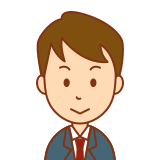
手当金の場合は、標準報酬月額ではなく、標準報酬日額で計算されるんですね
出産
出産育児一時金(被扶養者の場合は、家族出産育児一時金)
被保険者や被扶養者が出産したときに、子ども1人につき50万円が支給されます。
出産手当金
被保険者が出産のために会社を休み、その間、給与が支払われない場合、出産日以前の42日間(6週間)、出産後56日間(8週間)の範囲内で標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます(傷病手当金と同じ)
死亡
埋葬料(被扶養者の場合は家族埋葬料)
被保険者や被扶養者が死亡した場合、原則として、一律5万円が支給されます。
国民健康保険との差分について
これまで、健康保険について述べてきましたが、国民健康保険の場合は、以下の点が健康保険と異なります。
- 国民健康保険には、傷病手当金と出産手当金の給付がない
- 国民健康保険の加入者は全員が被保険者であり、被扶養者という制度がない
健康保険の任意継続被保険者
健康保険を退職後も継続して加入することができる任意継続被保険者という制度があります。この制度に該当するのは、退職前に健康保険に加入していた人で、退職後も引き続き健康保険に加入したい場合に適用されます。
- 任意継続の加入資格は、退職時に健康保険に加入していた期間が継続して2ヶ月以上必要です。
- 退職から20日以内に手続きを行うことが条件です。
- 任意継続の期間は、最長で2年間です。
- 保険料は、退職前に支払っていた保険料と同じ金額で、全額自己負担になります。つまり、企業が負担していた分も全て自己負担しなければならない点が特徴です。
後期高齢者医療制度
75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度では、年齢に応じた保険料が設定され、医療サービスを受けることができます。
- 75歳以上の人は、この制度に強制的に加入することになります。
- 医療費の自己負担割合は、原則として1割となっており、サラリーマンの健康保険とは異なる仕組みです(70歳以上=一律1割/2割/3割ではなく「所得に応じて区分あり」)
- 後期高齢者医療制度の保険料は、都道府県単位で異なります。
医療費の自己負担割合
【健康保険・国民健康保険】
| 被保険者・被扶養者の年齢 | 負担割合 |
|---|---|
| 6歳未満(小学校入学前まで) | 2割 |
| 6歳以上70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満(一般の所得者) | 2割 |
| 70歳以上75歳未満(現役並み所得者) | 3割 |
【後期高齢者医療制度】
| 被保険者の区分 | 負担割合 |
|---|---|
| 一般所得者等 | 1割 |
| 一定以上所得者 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 |
高額療養費
- 対象範囲: 1カ月(同じ月の1日~末日)の間に医療機関や薬局で支払った保険診療の窓口負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が支給されます
※「世帯合算が可能」「多数回該当では限度額がさらに引き下げられる」 - 自己負担限度額: 年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。例えば、69歳以下で年収約370万~770万円の人の場合、医療費の3割負担であっても高額な治療では限度額を超えることがあります
- 対象外項目: 差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療の技術料など、公的医療保険の対象外となる費用は含まれません
健康保険が使えないケースに注意
- 業務中や通勤中のけがは健康保険ではなく労災保険の対象です。
- この場合、保険証を出すのではなく「労災申請」が必要です。
試験で問われやすいポイント
- 日本は国民皆保険制度を採用している。
- 公的医療保険には3種類ある(健康保険・国保・後期高齢者)。
- 健康保険の給付対象には、病気・けが・出産・死亡が含まれる。
- 業務中の事故は健康保険でなく労災保険でカバーされる。
- 協会けんぽと組合けんぽの違いを理解しておく。
- 高額療養費の考え方を整理しておく。
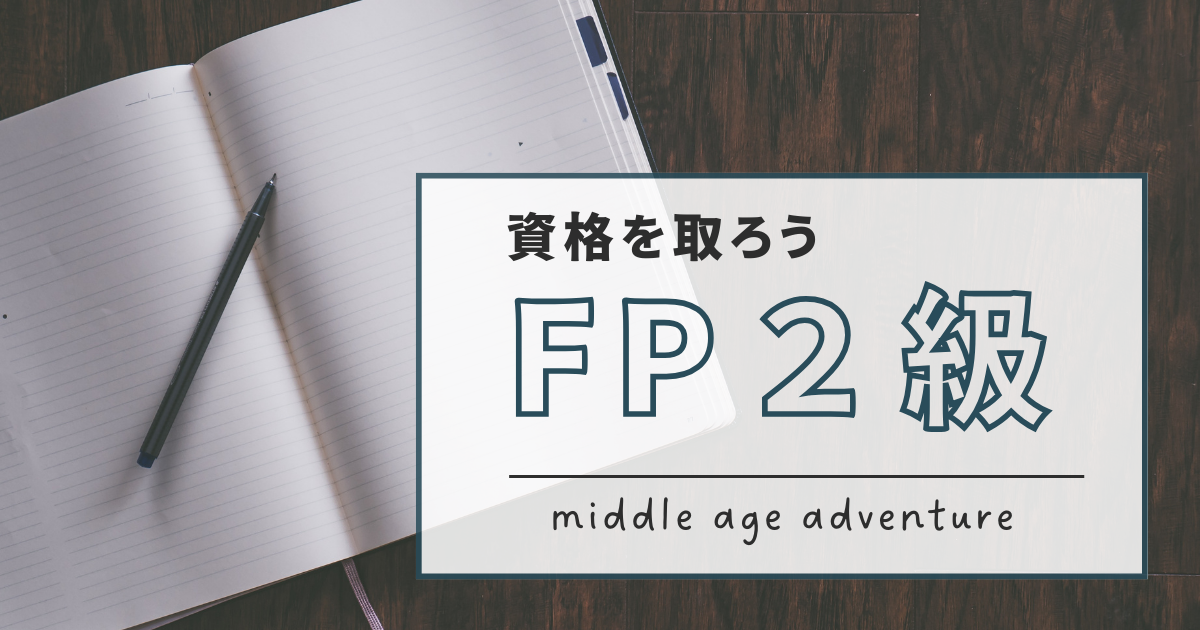

コメント