雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は、FP2級試験でも頻出の重要テーマです。
この制度は、働く人が失業したときの生活を支えるセーフティネットとして、一定の要件を満たした場合に国から給付金を受け取れる仕組みです。
この記事では、2025年6月時点の最新法令に基づき、以下のポイントをわかりやすく整理します。
- 受給資格要件(被保険者期間と離職理由の違い)
- 所定給付日数と年齢・勤続年数の関係
- 待期期間・給付制限・延長制度のしくみ
- FP試験で問われやすい出題パターン
制度の全体像を理解しておくと、学科試験の得点アップはもちろん、実生活での備えにも役立ちます。
それでは、雇用保険の基本手当を、FP2級の観点からやさしく整理していきましょう。
雇用保険の概要
- 雇用保険の保険者は、国(政府)で、その窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
- 雇用保険料は、失業等給付等・育児休業給付に係る部分は労使で負担し、雇用保険二事業に係る部分は事業主のみが負担します。
給付内容
給付内容は7種類と多く、ここで話題にする「基本手当」は、いわゆる失業手当のことで、失業後、休職中の生活費を支援する意味合いがあります。
| 雇用保険 | 失業給付 | 求職者給付 | 失業後就職活動中の生活費として ①基本手当 ②高年齢求職者給付金 |
| 就職促進給付 | 早期の再就職を支援目的のお祝い金 ③再就職手当 | ||
| 教育訓練給付 | スキルアップ支援金 ④一般教育訓練・専門実践教育訓練給付金 | ||
| 雇用継続給付 | 高齢者向け所得低下しても働き続けるための支援 ⑤高年齢雇用継続給付 ⑥介護休業給付 | ||
| 育児休業給付 | 育児による休職中のサポート ⑦育児休業給付 | ||
- 基本手当の給付条件は、離職日以前の2年間に被保険者期間(雇用保険料を払っている期間)が通算12か月以上あることです(ただし、会社都合による離職の場合は、直近1年間で6か月以上あれば対象となります)。
基本手当の給付日数
基本手当の所定給付日数(2025年6月時点)
◾ 自己都合・定年退職(一般受給資格者)
自己都合による基本手当の給付期間は、最短で90日、最長で150日間です。最長の給付を受け取れるのは、被保険者期間が20年以上ある場合です。
| 被保険者期間 | 所定給付日数 | 給付制限期間(離職日が2025年4月1日以降の場合) |
|---|---|---|
| 10年未満 | 90日 | 原則1か月(※例外あり) |
| 10年以上20年未満 | 120日 | 原則1か月 |
| 20年以上 | 150日 | 原則1か月 |
🟢 注釈
- 離職日が2025年3月31日以前は「2か月」。
- 過去5年以内に2回以上自己都合離職がある場合や懲戒解雇の場合は「3か月」。
- 待期期間7日+給付制限期間経過後に支給開始。
◾ 会社都合・倒産・解雇など(特定受給資格者)
| 年齢区分 | 被保険者期間6ヶ月以上1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | ― |
| 35~44歳 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | ― |
| 45~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
🔹 ポイント
- 給付制限はなし(待期期間7日のみ)。
- 年齢・勤続年数が長いほど給付日数も増加。
- 最大給付は「45~59歳・20年以上勤務」で330日(約11か月)。最長の給付日数を受け取れるのは、働き盛りで最も支出が多い世代に該当するため、そのように覚えておくと理解しやすいでしょう。
基本手当の受給期間
雇用保険の基本手当は、離職日の翌日から起算して原則1年間のあいだに受給しなければなりません。
この「1年」は、待期期間(7日)や給付制限期間(1か月など)も含めた通算期間として数えられます。
ただし、次のようにやむを得ない事情で求職活動ができない場合は、申請により受給期間を延長することができます。
- 病気やけがで働けない場合
- 妊娠・出産・育児によって就業できない場合
- その他、ハローワークが認める特別な理由がある場合
この延長は最大3年間まで可能で、もとの1年間と合わせて最長4年間となります。
(例:2025年4月1日に離職した場合、最長で2029年3月31日まで受給可能)
過去問
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用 保険の一般被保険者であった期間が通算して6ヵ月以上あるときに受給することができる。
2.基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の受給資格者は、被保険者期間が20年以上の場合、最長で180日である。
3.基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年である。
4.正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する基本手当は、待期期間満了後、原則として4ヵ月間の給付制限期間がある。
日本 FP 協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 19年年9月
最も「〇適切」な選択肢を選ぶ問題
- 基本手当の給付条件について問われている問題で、被保険者であった期間が通算して6か月ではなく、12か月でしたので、「×不適切」です。
- 一般の自己都合退職の最長は150日ですので、「×不適切」です。
- 基本手当の受給期間は、原則1年以内にもらい切らなくてはいけませんので、「〇適切」です。
- 待機期間後の給付制限は原則2か月間ですので、「×不適切」です。
(この過去問当時は)給付制限は原則2か月。なお、現在(離職日が2025年4月1日以降)は原則1か月(例外あり)。
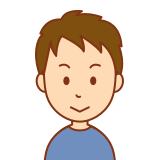
わたしは、「1年以内にもらうという点」が、理解できておらず、ほかの選択肢を選んでしまいました。
今回は、ここまでです。
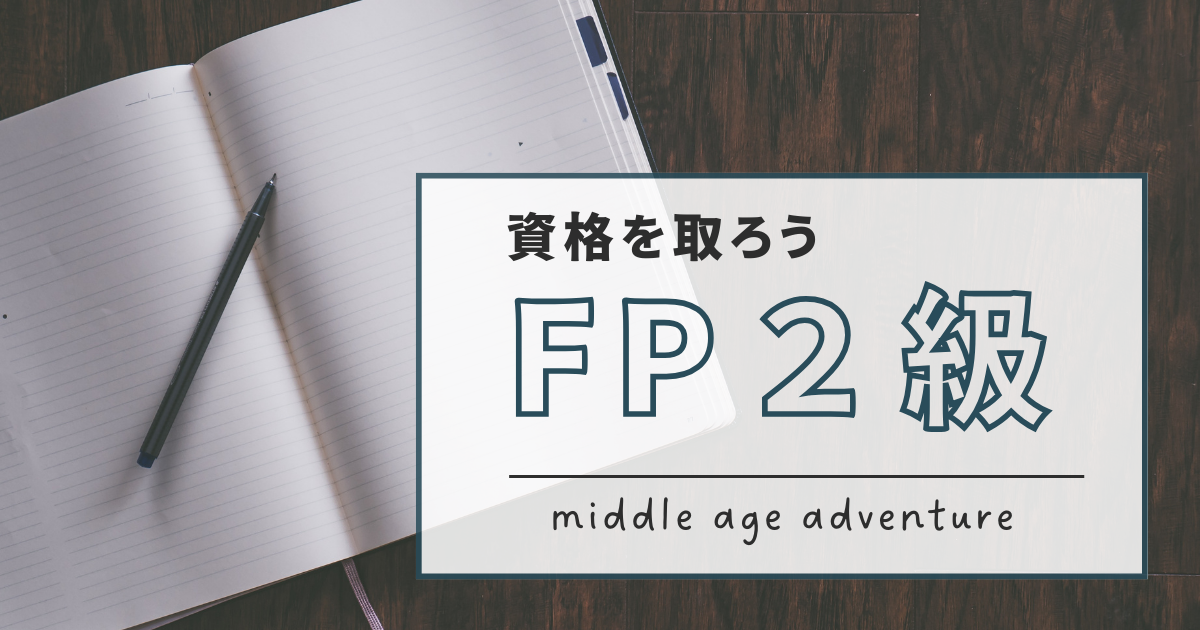
コメント